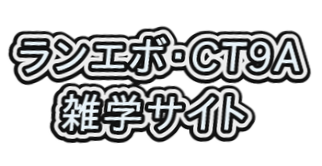自宅のクローゼットに置いてる、ランエボ おもちゃ箱。
箱に入るサイズの、小物パーツしか入れてないんですが、そこは30年物。
衣装ケースで3箱以上はあります。
中身は、新品の買い置きパーツだったり、交換はしたけど、まだ使えそうな中古品だったり。
あとは汎用品のホース類とか、ガスケット類なども。
別のケースには、ナットやボルト、ホースバンドやクリップ、スペーサーやシム類、たぶん一生分くらいあるかも?
こないだ箱をあさってたら、何年か転がったままだったパーツ、キャニスター用のチェックバルブがあるのを発見。
正直、いつ買ったのかも思い出せない。持ってることすら忘れてました。
こんなの。

通常、フューエル/キャニスターのチェックバルブといえば、画像上のMR312384のことを指しますが。
CT9A・ランサーエボリューションでは、下のMR497568の方も、フューエル/チェックバルブという名称になってます。
チェックバルブとは、ワンウェイバルブです。通常は閉じてて、ホースで繋がるパージ・ソレノイドバルブで制御されます。
このチェックバルブが経年劣化すると、普段は閉じてなきゃイケないバルブが、開きっぱなしになったりします。
こうなると、ここからエア吸いが発生してしまいますので、PCVバルブがヘタった時と同じような症状が出ます。
アイドリング不安定、アクセルオンでのエンジンストール、などですね。
*PCVバルブ交換記事は→こちら
私の悪魔のエボは、いまのところそんな症状はありませんが。
まあ、せっかく発見したし、簡単なんで予防交換しちゃいます。
チェックバルブ交換作業
場所なんですが。
イマドキのクルマは、チェックバルブは後部のガソリンタンクの近くにあるらしいですが。
その理由は後述しますが、ランエボはイマドキのクルマではありませんので、エンジンルーム内にあります。
ここ。

まず、黄色の矢印が指してるのが、チャコールキャニスター。
中身は活性炭で、役割はタンク内のガソリン蒸気を吸着してためとくコト。
大昔のクルマは、このチャコールキャニスターが無くて、タンクから大気開放してた。
でも今は規制があって、大気開放は環境汚染になるのでNG。
ガソリン蒸気は一旦、このキャニスターに貯めといて、パージソレノイドバルブで制御されてサージタンクに導かれて再燃焼されます。
このチャコールキャニスターも劣化するので交換が必要なんですが、今回はスルー。
理由は、走行性能にはほとんど影響ないから。たぶん。
劣化した時の症状は、ガソリンフル満タンした際、車内に少しガソリン臭が漂う程度。
あとは吸着能力が落ちるので、ガソリン蒸気が漏れ出ることがある。
イマドキ車が、このチャコールキャニスターをエンジンルーム内に持たないのは、クルマによっては、この漏れ出た蒸気がエキマニの熱なんかで引火する可能性があるから。
でもCT9Aの場合、仮に漏れ出てもシャシー下の空間から後ろに流されるレイアウトになってるので、エンジンルーム内にガソリン蒸気が溜まって引火、なんてことはまず無いかと。
後方排気レイアウトの、CZ4A・エボⅩなんかは、ひょっとしたら危険かも知れないですね。
というわけで、今回はバルブのみ交換。
といっても、ホースはとうぜん交換します。ここが劣化しててヒビ割れとかになってエア吸いしたら、せっかくバルブ替えても意味ないですから。
純正のホースではなく、おもちゃ箱の中にあった汎用品のホースを使いましたが、ここは純正を使うべきでした。理由は後で。
まずカンタンな、フューエル/チェックバルブの交換。
画像の黄丸のストッパーだけでハマってますから、ストッパーを持ち上げればスポン、と抜き取れます。

抜き取った状態。

このホース、どこにも繋がっておらず、開放状態。
たとえばチャコールキャニスターの劣化がヒドくなって、ガソリン臭が耐えられなくなったら、ここに汎用の長いホースを繋いで車体下から燃料ラインに沿わせてリアまで引っ張る、なんて対処方もあります。
まあ、そこまでしなくても、給油の時にオートストッパーが止まった段階で給油をやめる、つまり入れ過ぎないようにするだけでも、異臭騒ぎはかなり防げますけどね。
次は本命のチェックバルブとホース交換。
ここで私は、汎用品の手持ちのホースを使ったため、本来は不必要だった作業にムダな時間を取られました。
その理由ですが、この画像。

これは取り外した純正のホースとバルブなんですが。
見ての通り、純正のホースは特定の形状に成形された作りになってる。
これは例の、EGRなどのエミッションコントロール絡みのパーツが集中してる、サージタンク下、エンジン背部とバルクヘッドのスキマという、作業性サイアクの場所に向かっていくホース。
*この辺りの作業性の悪さを紹介する記事は→こちら
他のホースをかわしながら、パージ・ソレノイドバルブに繋がるため、こういったスペシャルな形状に成形されてるんです。
ところが使用したのは汎用の、ただのまっすぐなエラストマー製のホース。
これをウマく取り回して、ブレないようにタイラップで固定していくんですが、とにかく手が入らない場所なんで、片手でタイラップを回してノッチに通して締める、という曲芸をやるハメに。
最初から純正ホースを使っていれば、まったく不要な作業でした。
まずはカンタンな、チャコールキャニスター側。

ホースクリップを使用してますが、純正では何もありません。
たぶん、クリップやバンドなどの締め付けは不要なんですが、心配性なんで使っちゃいます。
次がちょっぴりやりずらい、サージタンク側。

見づらいですが、このニップルにホースの反対側を差し込みます。
ここはかなり奥側になるため、そうとう先が長い作りの特殊なホースクリッププライヤーが無いと、ホースクリップが使えません。
仕方がないので、タイラップで止めちゃいます。

まあ純正では、ただ刺さってるだけで、何も使われてないですからね。
後は前述の、ホースの取り回しを整えて終了。
予防交換なので、作業後も何も変化はありませんが、一つ感心したコトが。
以前にバキュームホース類を予防交換した時にも、同じことを思ったんですが。
製造から24年、走行距離が21万キロオーバーの車体ですが、ゴムホース類の劣化が少ないんですよ。
ぶっちゃけ、ひび割れや目視できるような劣化が見られず、触った感触もまだモチモチしてて素材としては生きてるカンジ。
ランエボのE/Gルームの灼熱地獄の環境にあって、ゴム類のこの耐久性は異常ですね。
これは、そうとうハイコスト/ハイクオリティの素材が使われてると思います。
やっぱり、2000年代中頃までの、日本の工業製品のクオリティはハンパないですね。
今の日本が失ってしまってる部分だと思うと、なんともやるせないです。